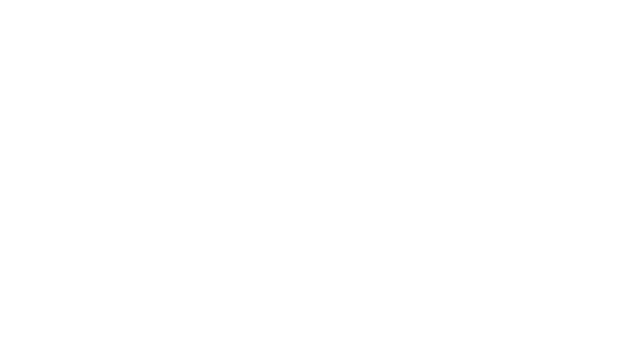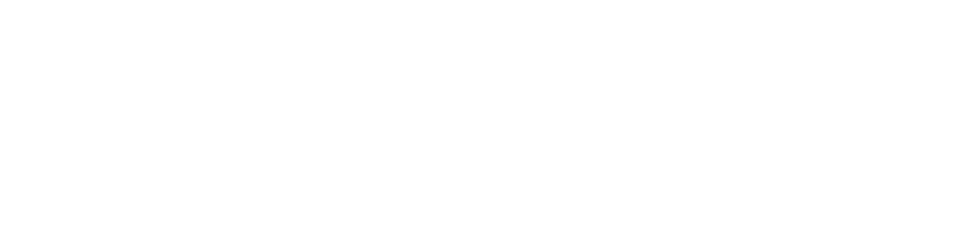手作りフリップ(12月23日放送)
「転換迫られる…原発輸出」
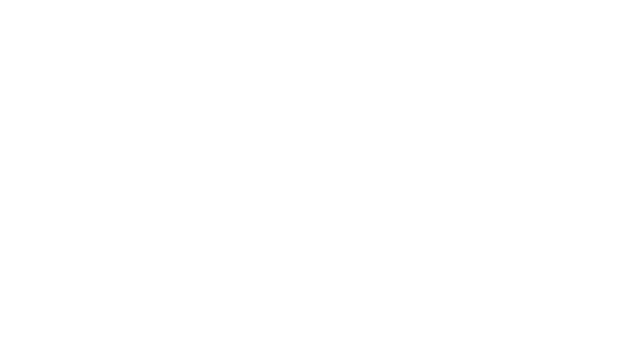
日立製作所の中西会長が述べた「限界」とは、イギリスで進める原発2基の建設計画のことで、「凍結する方向」で調整が行われています。
その最大原因は「建設費の高騰」です。
福島第一原発の事故後「安全基準が引き上げ」られ、安全対策などの費用が増加。当初の1.5倍3兆円まで膨らんでしまいました。
日立は国内の電力会社などに出資を求めたものの、巨額な投資に理解は得られず、断念した場合の損失は、最大2700億円にも上ることもわかりました。
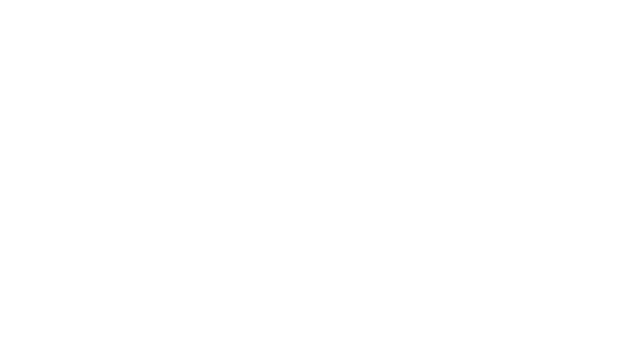
日本からの「原発輸出が暗礁に乗り上げた」のは、日立だけではありません!
第2次安倍政権がまず原発の売り込みに力を入れたのがトルコです。しかし三菱重工業などが計画している原発建設も、当初より建設費用が膨らむことが分かり断念の方向で検討が進められています。
更にベトナムでも、日本政府との間で受注が決まっていた計画が、建設費高騰などで白紙に。原発輸出は、安倍政権が「成長戦略に掲げるインフラ輸出の柱」でしたが、暗礁に乗り上げる形となりました。
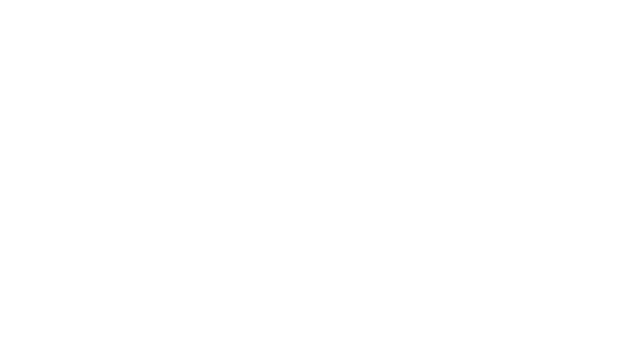
「民間企業が進める原発輸出」にも逆風が吹いています。
リトアニアや台湾では反対運動が高まり凍結されました。更に海外の原発事業としては、東芝の子会社がアメリカで原発事業を手がけていましたが、破綻、撤退しました。
そもそも原発に対する「世界的な逆風」は、福島第一原発事故以降、吹き続けていました。
安全策強化で膨れあがった建設費は、電気料金にも跳ね返り「原発は安い電源ではない」とする指摘や、「日本の原発そのものに対する不信感」を指摘する声もあるといいます。
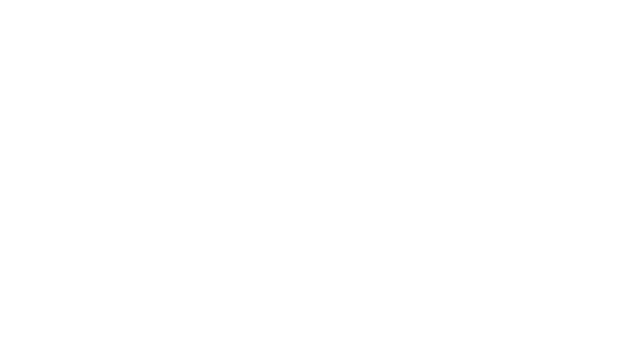
更に逆風となっているのが「再生可能エネルギーの普及」です。
国際組織による指標では、太陽光や風力などの再生エネルギーの発電容量が、2011年頃には原発を抜いており、エネルギーの専門家で作る国際組織の議長は、「再生エネルギーがコスト削減で競争力のあるエネルギー源になった」と指摘しています。
現在58基の原発を抱えるフランスでも先月末、マクロン大統領は、「原発依存度を現在の75%から2035年までに50%まで減らす」と表明しています。
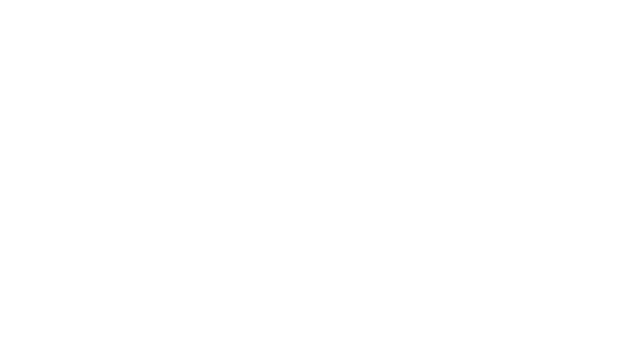
こうした中、日本の原発輸出政策は行き詰まっているかと問われた、菅官房長官は、「日本の原子力技術に対する期待の声はある」と強調しましたが、原発輸出戦略は見直しを迫られそうです。