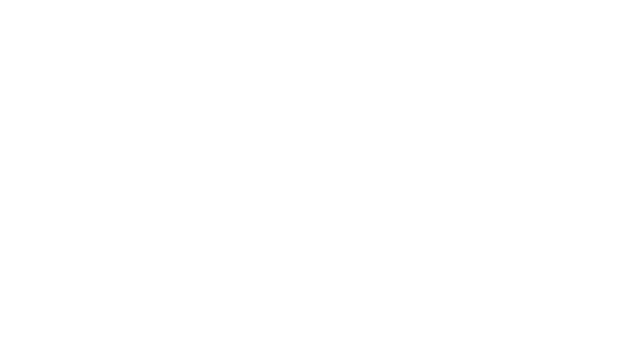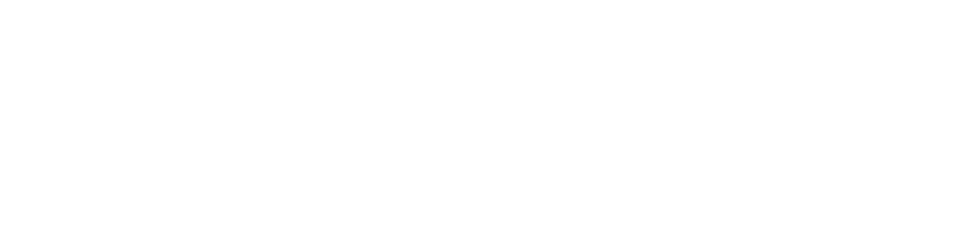手作りフリップ(2020年10月4日放送)
「廃止?ハンコの歴史は」
※ 一部端末では動画がうまく再生できない場合がございます
行政手続きで、ハンコの使用を原則廃止するよう求めている河野行政改革担当大臣。 これは以前、ある中央官庁で使用されていたという公文書です。 赤い印がついているのがハンコを押すところなんですが、1枚でおよそ20か所もあるんです。
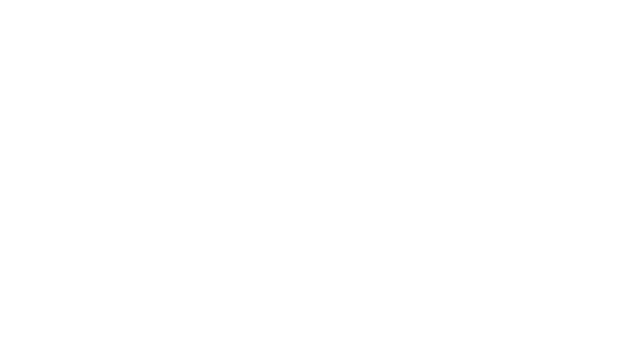
今まで慣例的にハンコを求めてきたことに、防衛大臣だった時、河野氏は「コロナの状況で果たしてハンコが必要なのか、業務の効率化を考えると、どうにかしなくてはならない」と苦言を呈していました。
そもそもハンコを押すというのは、所有権を明らかにしたり、契約行為を確認したりするためのもの。 ハンコが日本で初めて使われるようになったのは701年に制定された「大宝律令」がきっかけです。
天皇が所有するハンコ・天皇御璽や太政官印など4つの「官印」が作られ、ハンコによる行政処理が始まりました。
中でも、天皇御璽は公文書や国家の機密文書に押されていたと言われています。 ハンコの歴史に詳しい大阪芸術大学の久米客員教授は、「中央省庁の重要書類にハンコを押す文化は、この時から始まった」といいます。
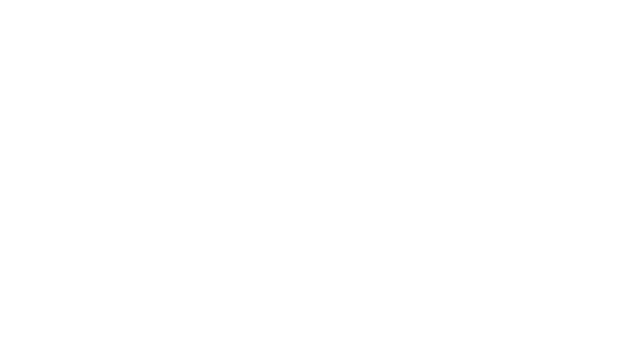
そんなハンコが、一般の人にまで広がったのは江戸時代のことです。 農民や町人は紙などに押したハンコの跡を、町役人に届け出ることが義務づけられ、 このハンコの跡を「実印」と呼びます。 金銀の貸し借りや、家屋敷の売買などのあらゆる証明書に、届け出たハンコを押すことが必要となりました。
江戸時代におけるハンコの習わしが法令によって定められたのが、明治時代のこと。 1873年、実印のない証明書は法律上、証拠とならないとする「印鑑登録制度」が整備されました。
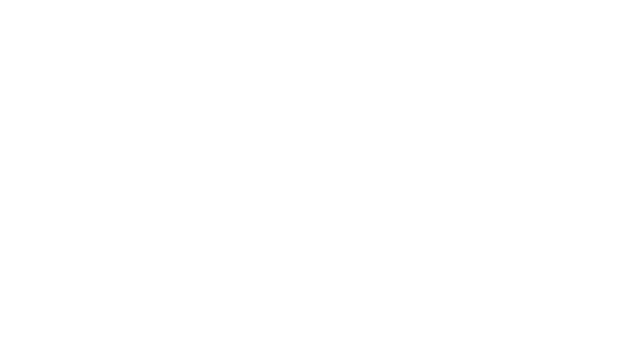
これにより、原則として実印を持たなければならなくなり、今のように、ハンコがより身近な存在となりました。
もともと6000年ほど前にメソポタミアから始まり、シルクロードなどを経て日本に伝わったとされるハンコですが、今世界に目を向けてみると、個人のハンコが広く使われているのは、日本を含め、韓国と台湾だけなんです。これは、戦前の日本統治時代に導入した名残と言われています。
こんなことわざがあります。「印形は首と釣り替え」。 ハンコを押すことは、首と引き換えにするくらいの覚悟がいるという意味で、滅多なことでハンコを押してはいけないと戒められています。 新型コロナの影響もあり、使われ方の見直しが迫られているハンコ。 今、大きな転換点に立っています。